藤井風の「花」──コード進行が生み出す美しさの秘密
こんにちは。私のブログにお越しいただき、ありがとうございます。
今回は、藤井風の楽曲「花(はな)」について、少し音楽的な視点からその魅力を掘り下げてみたいと思います。
特に、「コード進行」に注目しながら、藤井風ならではの表現力とセンスに迫っていきます。
音楽理論の難しい話はできるだけ避けつつ、どなたでも楽しめる内容を目指しました。
ぜひ最後までお付き合いください。
藤井風の花はレトロでおしゃれ──イントロのコードが描く世界観
「花」が始まった瞬間、私たちはまるで時間が巻き戻されたかのような、懐かしくて温かな空気に包まれます。
低音のピアノが静かにリズムを刻むこのイントロは、まるで70〜80年代の洋楽バラードのよう。けれど、決して古臭くはなく、「今」の音楽として洗練されているのが不思議です。
その秘密のひとつが、シンコペーションという奏法です。
リズムがずれることで自然な揺れが生まれ、思わず体を左右に動かしたくなるような、優しいグルーヴが感じられます。
このイントロだけで、藤井風さんの音楽に深く引き込まれてしまう方も多いのではないでしょうか。
藤井風の工夫、シンプルなのに深い──「花」のコード進行
「花」のキーはE♭(ホ長調)で、基本的な構成はとてもシンプルな循環コードです。
どの時代にも多くの楽曲で使われてきた、いわば「王道」の進行。それにもかかわらず、藤井風さんが弾くと、なぜこんなにも美しく、洗練された響きになるのでしょうか?
その秘密は、コードに加えられたテンションやオンコードにあります。
テンションとは、コードに加えられる装飾音のこと。例えば「9th」や「11th」など、主音から少し離れた音を重ねることで、和音に奥行きと彩りが生まれます。
また、オンコードではベース音を変えることで、コードに動きを与えています。
つまり、同じコードでも、ちょっとした工夫で印象ががらりと変わるんですね。このあたりのセンスが、藤井風さんの音楽の大きな魅力の一つです。
サビで訪れるドラマ──転調と代理コードの妙
サビの前半も引き続きシンプルな進行ですが、中盤から音楽の表情が大きく変わります。突然訪れる転調により、感情の波が一気に高まるのです。
ここでは、キーがE♭からC(ハ短調)へと変わります。長調から短調への変化は、どこか心に影を落とすような切なさを生み出します。
さらに、コードに♭5や♭9といった、ちょっと不安定な響きを加えることで、聴き手の心を揺さぶります。
そして注目すべきは、サビの終盤で使われる代理コード。
これは、本来のコードの代わりに機能するもので、藤井風さんの楽曲ではたびたび登場する技法です。
サビの11小節目にさりげなく使われた代理コードが、思わず「おしゃれ!」と唸るような響きを作り出しています。
最後のコードがI(主和音)ではなく**Ⅵ(C7)**で終わることで、次のセクションへ自然に橋をかけるような構造になっており、全体の流れにも無理がありません。
こうした構成力の高さも、藤井風の音楽的才能を物語っています。
藤井風の技術、間奏に潜む魔法──コードが描く新たな風景
曲が進むにつれて訪れる間奏。
ここでは、イントロやサビで使われていなかったコードが登場し、曲に新たな彩りが加わります。
特に印象的なのが、**D♭M7(9)**というコード。これは、とても柔らかく幻想的な響きを持つコードで、間奏の冒頭にふさわしい「異世界への入り口」のような存在感があります。
面白いのは、このD♭M7(9)とイントロのFm7が、実は構成音がとても似ていること。
ベース音を3度下げるだけで、他の音は共通しているのです。こうした「見えないつながり」が、曲全体のまとまりを生んでいます。
この間奏部分も引き続きCマイナー(ハ短調)の世界観で展開されており、少し不安定で、まるで夢の中を彷徨っているような感覚を与えてくれます。
藤井風のまとめ方、そっと終わる美しさ──エンディングの余韻
ラストのサビが終わると、藤井風さんのピアノが再び前面に出てきます。
アルペジオ(分散和音)で優しく奏でられるフレーズが、どこか温かく、それでいて寂しげな響きを残していきます。
コードそのものは変わらずとも、音の数が徐々に減っていくことで、まるで音楽そのものが静かに眠りにつくような感覚に包まれます。
最後は、ベース音さえも消え、余韻だけが静かに残る──。
それはまるで、心に咲いた一輪の花が風に揺れて、静かに散っていくような、美しい終わり方です。
この曲には、コードの中に咲く「花」の魅力があるのですね。
さて如何でしたか? 今回は、藤井風の「花」という楽曲を、コード進行という視点から読み解いてみました。
「懐かしさ」と「新しさ」が共存するこの楽曲は、シンプルでありながら、随所に工夫が凝らされたコード使いによって、深い情感を表現しています。
コード進行というのは、楽曲の骨組みにあたる部分ですが、そこにどんな「色」を加えるかで、聴こえ方はまったく変わってきます。
そして、藤井風はその「色づけ」が本当に巧みなのです。
歌詞やメロディの美しさはもちろんですが、こうした細部のコード設計にまで目を向けることで、「花」という楽曲がさらに豊かに感じられるはずです。
最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。
また別の記事でも、藤井風さんの音楽の魅力について語れたら嬉しいです。
ぜひ今後も、当ブログをよろしくお願いいたします♪

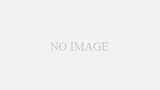
コメント